『価値づくり』の研究開発マネジメント 第349回
普通の組織をイノベーティブにする処方箋(196): KETICモデル-思考(138)
「発想のフレームワーク(73):隣接可能性とは(1)」
(2025年2月3日)
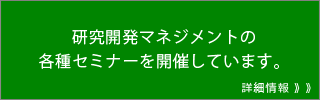 |
ここまで随分長きにわたり「妄想を積極的に促す方法」について、議論してきましたが、今回からテーマを変えて、「隣接可能性」について考えてみたいと思います。
●隣接可能性とは
これまでこのメルマガの中でも、また私のセミナーの中でもかなりの頻度でこの「隣接可能性」について言及してきました。まず隣接可能性とは、どのようなものでしょうか?
Chat GPTに聞いてみたところ、以下の説明がありました。
隣接可能性(Adjacent Possible)とは、生物学者スチュアート・カウフマン(Stuart Kauffman)が提唱した概念で、現在の状況から「すぐに到達可能な」新しい可能性の範囲を指します。簡単に言えば、「今すぐ実現できる、次のステップとしてあり得る可能性」のことです。
(中略)
創造性の刺激
「まったく新しいものを考える」のではなく、「今あるもののすぐ隣にある可能性」を考えることで、新たな発見が生まれやすくなります。
●隣接可能性はイノベーションにおける必須の道具
シュンペーターによる有名なイノベーションの定義に、「イノベーションとは、既存の知識の新しい組合せ(新結合)」がありますが、組合せの対象の既存の知識はどのようなプロセスで新結合されるのでしょうか。
新結合は現実には、それまで「現状で意識していない」「遠くに離れている」2つの知識が、(何かのきっかけで)瞬時に遠くから手元にもってこられ、そこで新結合されるものではないと思います。実際に目の前にあるものや情報に触れて、「これと〇〇を組み合わせると面白くないかい?」と発想することで生まれるように思えます。すなわち、新結合の対象の2つの知識の内、きっかけになる新結合の片割れは、そもそも最初にそこにないといけません。その片割れに触れることで、その片割れの「何か」により触発されて、自分も普段はその存在を意識していない、自分の頭に長年の時間をかけて蓄積されてきた膨大な情報や経験を納めた蔵の中から、組合せの対象になる関連する情報をスキャンし引き出してくる。そういうプロセスを常に頭の中で行い、その何百、何千、何万の繰り返しの中から、組み合わせが「新しく」かつ「何か大きな価値を生む」数少ないものがイノベーションになるということだと思います。
すなわち、上で述べた「その片割れに触れることで、その片割れの「何か」により触発されて」の部分が、まさに隣接可能性によってなされるものです。したがって、この隣接可能性がどう生まれるか、どうしたら生まれやすくなるかは、イノベーションを生み出す上で極めて重要な部分ということになります。
すなわち、イノベーションを起こすために、重要なことが;
〇最初の片割れに触発されるというのはどういうことなのか?
〇どうしたら触発の頻度を高めることができるのか?
ではないかと思います。
次回からのメルマガの中で、これらの点について考えてみたいと思います。
(浪江一公)