『価値づくり』の研究開発マネジメント 第347回
普通の組織をイノベーティブにする処方箋(194): KETICモデル-思考(136)
「発想のフレームワーク(73):思考の頻度を高める方法(49) 妄想のすすめ(19)」
(2025年1月8日)
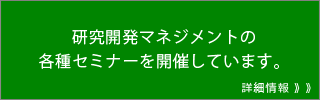 |
あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
前回、前々回は妄想のすすめとして、「遊びごころを持つ」というお話をしました。今回も引き続きこの議論を続けたいと思います。
●妄想を積極的に促す方法(その26):遊びごころを持つ(続き)
前回は、なぜ人間は「つらい」と考えるのかを分解して考え、2つの部分、すなわち、「問題解決や達成のハードルが高い」、「ハードルを越える能力に自信がない」に分けられ、これら2つへの対処法を講じることで、「つらい」という認識をポジティブなものに変えることができるという議論をしました。今回はこの2つのうち後者への対応策を考えてみたいと思います。
〇後者については、失敗することを自分の中で許容し、さらには失敗をポジティブに捉える
しかし、上の前者への対応策として前回議論したように「ハードルが高ければ高い程、達成の果実は大きい」と考え行動しても、いつもうまく行く訳ではありません。ハードルに挑戦し続ければ、必ず失敗は起こります。なぜなら、ハードルが高ければそもそも失敗の確率は高まるのですから。
そこでうまく行かなったこと、すなわち失敗を是とし、それをポジティブに考え積極的に受け入れるようにすることも重要です。そのために、以下の3つを理解し行動することが必要になります。
-「設定するに値する高いハードルに取組み続ければ、失敗はいつかは必ず起こる」という現実を受け入れる。
高いハードルを常にクリアすることは、人間がやる以上不可能です。またもし、常にクリアすることができたのなら、それら設定したハードルは、十分高いハードルとは言えません。むしろ、イノベーションを実現しようと思えば、時に失敗するようなハードルが、「高い」そもそも取り組むべきハードルなのです。そのような時に失敗するようなハードルを設定して、取り組まなければなりません。そのため、設定するに値する高いハードルに取組み続ければ、失敗はいつかは必ず起こるという現実を、大前提として受け入れる必要があります。
-高いハードルにチャレンジして失敗することで、得られる果実は大きいという事実に目を向ける
トーマス・エジソンの有名な言葉に、「失敗ではない。うまくいかない1万通りの方法を発見したのだ」があります。エジソンは、これまでしてきた様々な失敗の言い訳でこう言っているのではなく、本当にそう思っているのです。つまり、その失敗があれば、次はもっとうまくやれる可能性が高まります。さらにそれだけでなく、失敗を経験することで対象物に対する知識がおおいに高まり、今後の様々な取組に有効に働くからです。
-失敗しても高いハードルへの取組であれば、回りは失敗を受け入れてくれるもの
失敗してもそれが高いハードルへの取組であれば、会社を含めて回りの人達は、その事実そしてその姿勢を受け入れてくれ、さらには高く評価してくれるものです。それが、皆さんの打ち手に誤りがあっての失敗でもです。なぜなら評価する人達も、過去に必ず自分自身の打ち手の誤りに起因する失敗の経験をしています。会社人生を含め、長い人生の中で失敗をしたことのない人はいません。
しかし、もし皆さんの高いハードルへの取組結果の失敗に、会社や上司が罰で対応するようなことがあれば、そのような会社・人との関係を考え直した方がよいかもしれません。そのような会社・人は成長しませんし、皆さんの今後の長い人生において、良いことはないかもしれません。また、失敗し罰を加えられたら会社と縁を切るぐらい強い覚悟をもって取り組めば、むしろ成功の可能性はおおいに高まります。
(浪江一公)