『価値づくり』の研究開発マネジメント
第116回:「企業においてオープン・イノベーションを実現するには?(その2)」
(2015年10月5日)
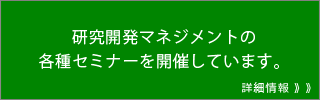 |
前回は、オープン・イノベーションは、それ単独では社内で浸透、実行されることは困難であり、『価値づくり』の経営の追求とセットでなければならないという話をしました。それでは、具体的にどうすれば社内でオープン・イノベーションが実行されるかを、今回から数回を使って議論していきたいと思います。
●オープン・イノベーションの阻害要因;QCD一辺倒主義
先日、私が教員を務めるMOT大学院でゲストスピーカー(大手自動車部品メーカー管理職)をお呼びし、あるテーマでお話をしていただいたことがありました。そこでの冒頭の話が、利益は売価とコストの差で表されるが、利益を増やすには、売価を拡大することは大変難しいが、コストはゼロになるまで低減の可能性がある、そのため経営においてはコストの継続的な低減が経営のキーであり、その為のカイゼン活動を徹底して行っているということでした。
ゲストスピーカーとしてお呼びしておいて、このようなことを言うのは甚だ失礼ではありますが、驚くことに、この企業のように、大手企業を含め、未だQCDの妄想に捉われて経営をしている企業が多いということです。このような企業においては、その社員にとっては、オープン・イノベーションは宇宙の彼方の概念であり、それこそ『妄想』の領域の議論です。ほとんどオープン・イノベーションの実行は不可能でしょう。
●QCD一辺倒主義の払拭の難しさ
オープン・イノベーションを実現するためには、全社的にもQCD一辺倒の経営から脱却した上で、『価値づくり』経営の追求転換することが必須です。
もちろんそれは簡単ではありません。社内にはQCD一辺倒主義勢力が組織の隅々まで、存在しています。それは、経営陣も含めてです。なにしろ長年に渡り、経営陣が旗を振り、そのための活動を精力的に進めてきたのですから。それに加え、日々競合企業と戦い、顧客と対峙している現場においては、どうしてもQCD一辺倒に傾いてしまいます。例えば、自動車部品業界では、品質問題を原因とした経営に多大な影響を与えるリコールなどの問題があり、ますますQCD一辺倒主義に流れてしまいます。更には、経営陣にとってQCD一辺倒主義の経営は、誤解を恐れずに言えば、簡単です。何しろ、上での述べた企業のように、ひたすら現場での目先の活動を進めていれば良いのですから。
日立製作所で改革のリーダーとして活躍した、川村隆氏(現相談役)は、日本経済新聞の「私の履歴書」の中で、日立製作所が大きな赤字を計上した改革以前の副社長時代を振り返り反省して、以下のように語っています。これはQCDに限定した話ではありませんが、日々の日本企業の経営陣の関心を象徴的に示しています。
「これだけの多くの分野を管轄しているのだから、忙しいことは忙しい。社内の会議が終われば、客先に出向き、午後は日立が納めた発電機の運転開始セレモニーに出席する、といった具合でスケジュール帳はいつも真っ黒。海外出張先からテレビ会議で本社の会議に出席することもしばしばだった。だが、なぜか自分の中で「しっかり仕事をした」という実感が湧いてこない。この時期世界的なIT不況で日立は5千億円近い巨額の赤字を計上し、希望退職を募るなど危機の時代だった。・・・・それなのに日々膨大が仕事量に流されることを良しとしてしまった。自覚は無かったが、一種の逃避をしながら懸命に働いているという形を作っていた、と言われても仕方がない。忙しく髪を振り乱して働いている人間が本当の仕事をしているとは限らないことが分かった4年間だった。」
●QCD一辺倒主義の払拭の難しさを乗り越えて『価値づくり』経営にコミットする
そのため、まずは出発点として、長期の全社の経営の方針として『価値づくり』経営に舵を切ることを、経営レベルでコミットしなければなりません。『価値づくり』経営は、QCD一辺倒経営に比べ、遥かに複雑で困難な道です。なぜなら、QCD一辺倒主義が、目先の重要顧客と身内である社員だけを対象に経営をしていれば良かった一方で、『価値づくり』経営では、外部の様々なステークホルダとの広く、複雑なコミュニケーションを前提としているからです。それに、経営の基盤としては、やはりQCDの継続的向上も同時に行って行かなければなりません。
しかし、これをせずして、オープン・イノベーションの果実を手に入れようとしても、本当に極一部の効果しかありません。それにそもそも、QCD一辺倒の経営では、先細りは明らかです。
オープン・イノベーションを推進しようとするならば、企業の経営陣は、勇気を持って『価値づくり』経営の転換に踏み出さなければなりません。
(浪江一公)