日本企業復活の処方箋「ステージゲート法」
第67回: 「顧客のライフサイクル全体に目を向ける」
(2013年11月11日)
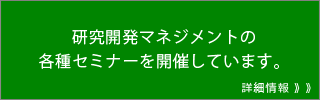 |
前回は2つ目の軸の「分野軸(Area)」の「広義の市場に目を向ける」を議論しましたが、今回は「顧客のライフサイクル全体に目を向ける」を議論したいと思います。
●顧客のニーズの発生時期:ライフサイクル全体
顧客は自社の製品を購入するに当たり、様々なニーズや関連する課題を持っています。それは、製品の購入のずっと以前から始まり、自社の製品の寿命が尽き廃棄するまで続きます。場合によっては原子力発電所の核廃棄物のように、廃棄後も続く場合もあります。
この過程すべてにわたり顧客は何かしらの活動や検討を行い、またそこには顧客のコストが発生しています。従って、顧客はこのような活動の開始から廃棄までのプロセスすなわちライフサイク全体のことを考えて購買の決定をする傾向があり、顧客にとってその製品が重要で全プロセスで負担するコスト全体が大きければこの傾向は益々強くなります。
このように顧客のライフサイクル全体は、自社が供給する製品と密接に関係し、自社の製品やサービスをデザインする場合に考慮すべき様々なポイントが含まれています。そのため、企業としては、顧客のこのライフサイクル全体に目を向け顧客・市場を理解しなければなりません。
●ライフサイクルの後半:顧客が購入を決定し廃棄するまで
最近の日立製作所の動きには目を見張るものがあります。以前は、世の中では日立というと技術レベルは高いものの、気位ばかり高く、彼らの競合企業であるGEに比べ利益率ははるかに低く、まさに重く愚鈍な重電機メーカーと思われてきました。しかし、2008年の巨額連結赤字(7873億円)の後の経営陣の刷新により、日立は別の会社に生まれ変わったという感じがしています。例えば、英国では鉄道車両を大量に受注したのみならず、車両の長期保守(27年)というサービスも積極的に提供するようになっています。車両受注の金額は高額に上りそれだけでも企業としては魅力的ではありますが、顧客の立場から言うと車両の購入後の運行にはそれ以上のコストが必要とされます。日立として、顧客の車両購入後も引き続き関連する保守サービス事業を展開することで、収益機会が拡大します。また、ハードとサービスの両者を手掛けることで、保守コストを含めた運行コスト全体を低減する車両、また車両コストを低減する保守サービス、つまり両者の最適化をすることが自社のコントロールの中で実現することができるようになります。
当然この成果物は顧客の全体コスト低減・サービス向上という形でも還元され、日立そして顧客の両者がWIN-WINの関係の中でそれぞれ果実を得ることができるようになります。
その他に建機メーカーの例があります。建設機械は購入時の価格が高額であるだけでなく、その後の運用・維持コストや下取りの価格は、顧客である建設業者のコストに大きく影響します。従って、建機メーカー側で、できるだけ維持・運用コストを下げると同時に、下取り価格を高く維持する方法を考え提供することは、顧客にとっては大変ありがたいことです。近年建機メーカーはコマツのKOMTRAXを初め稼働状況をモニターする機器を建機本体に設置しそこから得られる運転情報により、稼動時間に応じ部品の交換を提案したり、燃費効率を上げる運転法の指導などを行うようになっています。これにより、顧客は運転・維持コストを下げ、また同時に自社の建機を良い状態に保持することで下取り価格を高く維持することができるようになります。
以上の日立の鉄道車両やコマツの建機の例では、顧客が負担するコストが高いため、既にこの考え方が導入されていますが、消費財を含めよりコストが低い製品についてもこのような考え方は今後メーカーに求められるようになるでしょう。
●ライフサイクルの前半:顧客が購入を決定するまで
研究開発の立場から言うと、顧客が購入を決定するまでは、営業やマーケティング部門の責任であり、研究開発とは関係がないと考えてしまいます。顧客に自社の製品を理解させ購入の意志決定まで至らせるには、製品の属性以外に研究開発が影響を与える部分はないと考えているからです。
私は、顧客の製品購入以前の自社の製品をマーケティングする活動にも研究開発が担う役割は存在し、今後その重要性は益々拡大するのではないかと考えています。顧客は製品の属性だけを見て購入を決定する訳ではありません。なぜなら、顧客は製品購入を決定する前に多くの作業を行ない、そこにコストを掛け、また様々な問題を持っているという事実があるからです。そこでも企業の頭脳である研究開発は、事業に貢献しなければなりません。
例えば、自社が金属部品メーカーであるとすると、顧客は自社に発注する前に部品を設計し部品図を作成する必要があります。そこには顧客の設計者がそれなりの工数を掛けていることが考えられます。そこで自社には、顧客の設計工数を削減する方法や顧客が作成した図面から直ぐに価格見積ができるソフトウェアの開発のニーズがあるでしょう。ここには、顧客が自社製品の購入前の作業を低減し、かつその作業と自社の製品を巧く組み合わせて、自社製品の受注の可能性を高めるという工夫は極めて有効です。もちろん、この例で言えば、既にCADは専門の企業が提供していて、いまさら自社の提供を考えることにはムリであるという意見もあるでしょう。実際そうかもしれません。しかし、このような視野を持って常に考えてみることが重要です。このような部分でも研究開発部門を活用することは、戦略的な効果も大きく、十分研究開発部門の対象とするに値するものです。
百歩譲って、製品購入に至るプロセスには研究開発テーマが関与する余地がないとしても、例えば新規事業を創出する研究開発テーマであれば、起案者である研究者やそのプロジェクトチームは将来のビジネスモデルを構想することが求められます。なぜなら、どのようなビジネスモデルで展開するかは、そのテーマが生み出す将来の新事業の収益を大きく左右する可能性があり、その研究開発テーマを手掛けるかどうかの決断に大きな影響を与えるからです。
以上のように、研究開発部門には、顧客提供価値の向上を実現するあらゆる機会に目を向け、研究開発活動を行うことが求められるのです。
(浪江一公)